雪が降った
2022/01/06
静かなるエッセイ 2022年1月6日 雪が降った
一年の始まりにはいつも、今年はどんな年になるのだろう、と期待と不安が入り交じる。安泰が一番だけれど、時には心に真っ赤な火がつくような、ドラマチックなことも起きて欲しいと思う。あるいは過ぎ行く時の速さを想い、また一つ歳をとるのだと愕然となることもある。夫の仕事、年老いた親、子供たちのための活動、そして自分の仕事のことなどが、唸る蜂のようにめまぐるしく頭の中を飛び交う。でも良くしたもので、暮らしと生業の騒々しさが、そんな危惧をいつのまにかどこかに忘れさせてくれる。だから成り行きに任せていられるのだろう。
「あまり深刻に考えても駄目ですね。どうにかなりますから、暮らしを楽しみましょう」と言うオプティミストの夫とペシミストの妻、この組み合わせはなかなかいいものだ、と自画自賛。物事をあまり楽観視し過ぎるのも危ないし、悲観ばかりでもつまらない。お互いに牽制し合い、その中庸をとって結婚36年。 結婚してから何回もあった転機を、夫の言うように明るく切り抜けてきたものだった。私の流産、夫の転職、そして転居。転々と転がる石のように……Like a rolling stone(ディラン)ではなく、けっこう真剣に考えて。
中でももっとも決心の要ったのが転居である。東京に生まれ育ち、東京でキャリアを積んできた私。働き盛りの三〇代と四〇代が、突然地方の農村に引っ越すと言うのだから、これが事件でなくてなんであろう。東京の回りの人たちは皆、仕事は大丈夫? と心配してくれた。私たちにもどうなるのか分からなかったが、夫は「ご心配なく」と涼しい顔。そして今やその通りになった。
新しい土地での私たちの強い味方は、大いなる自然である。心細いとき、寂しいとき、我家を360度に取り巻いている自然と向かい合うと、不安や孤独感を忘れることができるのだ。冬の澄み切った空気で磨かれたような青空は、閉じそうになる気分を晴れ晴れと輝やかせてくれる。
森や林から聞こえてくる葉のざわめきと、小鳥たちの歌う子守歌に、私たちはいつかまどろむ。山々や大地、太陽を吸い込んだ温かい海は、にっこりと微笑んでいるよう。母親の懐のぬくもりがよみがえる。
都会育ちの私たちの、ぎこちない暮らしぶりをお手伝いしてくれるのも、余りあるたくさんの自然。夫が耕す小さな菜園に、野菜が勢い良く育ち、野原には食べられる草が次々と生え、木にはたわわに実がつく。私たちはそれを食べて命の糧とし、生きている。
でもやはり、人様の力添えもどんなに有り難いことか。近しい人人々の実際的な助力や遠くからの声援。それに負けないくらい、夫と私も助け合わなければ、この田舎では暮らせない。
東京では、別々のことをしていた二人だが、ここではどちらからともなく力を貸し合うのが当たり前になった。仕事も共同作業。これも自然のお陰。その自然と共に行く今年を、平和で良い年にしよう。と、思うが、コロナのパンデミックでは思ったようなことが出来ない。だから自分だけに出来ることをしている。
冬の贈物の中で、私が届くのを心待ちにしているものがある。それは雪。
今日1月6日、ついにこの暖かさで知れる房総半島にも雪が降った。すると私の今日は特別なものになる。家の外や景色や、そして私の雑念などの現実の醜さを隠してくれるからだ。
天から舞ってくる雪を飽かさず眺めていると、私のつまらない感情は無になる。そして庭の向こうにある谷間へ吸い込まれていく雪と共に、私自身も、無限の彼方へ旅をし、心の浄化を体験する。
足跡のついていない処女雪の上を歩くのもまた、幻想的だ。この世で初めて、二本の足でそこを踏み付けるのはこの私だから、なんとなく震えがきてしまう。でも、レイモンド・ブリックの『スノーマン』のように、雪だるまと一緒に空を飛べたらなあ、とも思う。
雪を食べるなんてロマンチックだが、悲しみの中で食べる人もいる。宮沢賢治は亡くなった妹に、氷結の朝、雪を与えた、と詩に書く。ある現代女性作家は、「雪をグラスに入れて、ジャムをのっけて食べるのよ」、と楽しげに言う。
風が流す雪と共に、時々我が家に、とても可愛い小さなお客が訪れる。ある時は小鳥、ある時は野兎。雪の下に埋められた餌を得られずに、我が家に食事への招待を求めてくるのだ。小鳥には御飯粒やパン屑を、野兎には、キャベツや人参の切れ端を、庭のピクニック・テーブルの上に置いてやる。
慎ましい彼等は、すぐには食卓につかない。私がテーブルを調えるのを、はるか向こうでじっと待ち、私が家の中に入ると遠慮がちにテーブルに近寄り、そして、誰か他のお客が同じご馳走を待っていないかどう探り、もしいるとしたら、まず彼等に先をゆずり、そうして初めて、おちょぼの口元にほんのわずかの食事を運ぶのである。
おなかが空くから食べる、からだを暖めるために食べる、子供のために食べる、と動物たちの食べ方はとても本能的だけれど、それだけに、目的が果たされればそれ以上の量は食べない。利己的でも飽食でもない。
「外に出てきてごらん、野兎が……!」
悲鳴にも似た夫の呼び声。駆け付けてみるとどうだろう、わが愛犬が、野兎を無我夢中で貪っているのである。ハンターが山に入って撃ち、猟犬が見つけ損ねた獲物を、放し飼いの犬がありついたのだ。
私は犬を叱る気にはなれなかった。それが動物たちの自給のあり方であり、自分の命を他のものに食物として与えるという、食物連鎖の宿命であるからだ。彼等は、分け合って食べるための丸いテーブルを持っている。
それにひきかえ、人間はどうだろう。世界各地で戦争や自然破壊をし、罪もない子供やお年寄りを飢えさせている。その引き金を引いた者が、食物や利益を貪っているのだ。そして今日、この雪の寒さに震え、食事もできず、温かな寝床もない若者を含む多数の人々が、コロナ禍のために苦しんでいるのだ。そんな報道を観ると、なんとかして上げたい、と思うのだが、それ以上に、そんな人々を助けない政治に怒りが爆発する。
ああ、真っ白な牡丹雪が吹雪く。雪よ、この真っ黑と化した世界を、真っ白な清潔さで、清浄にして欲しいのです。
一年の始まりにはいつも、今年はどんな年になるのだろう、と期待と不安が入り交じる。安泰が一番だけれど、時には心に真っ赤な火がつくような、ドラマチックなことも起きて欲しいと思う。あるいは過ぎ行く時の速さを想い、また一つ歳をとるのだと愕然となることもある。夫の仕事、年老いた親、子供たちのための活動、そして自分の仕事のことなどが、唸る蜂のようにめまぐるしく頭の中を飛び交う。でも良くしたもので、暮らしと生業の騒々しさが、そんな危惧をいつのまにかどこかに忘れさせてくれる。だから成り行きに任せていられるのだろう。
「あまり深刻に考えても駄目ですね。どうにかなりますから、暮らしを楽しみましょう」と言うオプティミストの夫とペシミストの妻、この組み合わせはなかなかいいものだ、と自画自賛。物事をあまり楽観視し過ぎるのも危ないし、悲観ばかりでもつまらない。お互いに牽制し合い、その中庸をとって結婚36年。 結婚してから何回もあった転機を、夫の言うように明るく切り抜けてきたものだった。私の流産、夫の転職、そして転居。転々と転がる石のように……Like a rolling stone(ディラン)ではなく、けっこう真剣に考えて。
中でももっとも決心の要ったのが転居である。東京に生まれ育ち、東京でキャリアを積んできた私。働き盛りの三〇代と四〇代が、突然地方の農村に引っ越すと言うのだから、これが事件でなくてなんであろう。東京の回りの人たちは皆、仕事は大丈夫? と心配してくれた。私たちにもどうなるのか分からなかったが、夫は「ご心配なく」と涼しい顔。そして今やその通りになった。
新しい土地での私たちの強い味方は、大いなる自然である。心細いとき、寂しいとき、我家を360度に取り巻いている自然と向かい合うと、不安や孤独感を忘れることができるのだ。冬の澄み切った空気で磨かれたような青空は、閉じそうになる気分を晴れ晴れと輝やかせてくれる。
森や林から聞こえてくる葉のざわめきと、小鳥たちの歌う子守歌に、私たちはいつかまどろむ。山々や大地、太陽を吸い込んだ温かい海は、にっこりと微笑んでいるよう。母親の懐のぬくもりがよみがえる。
都会育ちの私たちの、ぎこちない暮らしぶりをお手伝いしてくれるのも、余りあるたくさんの自然。夫が耕す小さな菜園に、野菜が勢い良く育ち、野原には食べられる草が次々と生え、木にはたわわに実がつく。私たちはそれを食べて命の糧とし、生きている。
でもやはり、人様の力添えもどんなに有り難いことか。近しい人人々の実際的な助力や遠くからの声援。それに負けないくらい、夫と私も助け合わなければ、この田舎では暮らせない。
東京では、別々のことをしていた二人だが、ここではどちらからともなく力を貸し合うのが当たり前になった。仕事も共同作業。これも自然のお陰。その自然と共に行く今年を、平和で良い年にしよう。と、思うが、コロナのパンデミックでは思ったようなことが出来ない。だから自分だけに出来ることをしている。
冬の贈物の中で、私が届くのを心待ちにしているものがある。それは雪。
今日1月6日、ついにこの暖かさで知れる房総半島にも雪が降った。すると私の今日は特別なものになる。家の外や景色や、そして私の雑念などの現実の醜さを隠してくれるからだ。
天から舞ってくる雪を飽かさず眺めていると、私のつまらない感情は無になる。そして庭の向こうにある谷間へ吸い込まれていく雪と共に、私自身も、無限の彼方へ旅をし、心の浄化を体験する。
足跡のついていない処女雪の上を歩くのもまた、幻想的だ。この世で初めて、二本の足でそこを踏み付けるのはこの私だから、なんとなく震えがきてしまう。でも、レイモンド・ブリックの『スノーマン』のように、雪だるまと一緒に空を飛べたらなあ、とも思う。
雪を食べるなんてロマンチックだが、悲しみの中で食べる人もいる。宮沢賢治は亡くなった妹に、氷結の朝、雪を与えた、と詩に書く。ある現代女性作家は、「雪をグラスに入れて、ジャムをのっけて食べるのよ」、と楽しげに言う。
風が流す雪と共に、時々我が家に、とても可愛い小さなお客が訪れる。ある時は小鳥、ある時は野兎。雪の下に埋められた餌を得られずに、我が家に食事への招待を求めてくるのだ。小鳥には御飯粒やパン屑を、野兎には、キャベツや人参の切れ端を、庭のピクニック・テーブルの上に置いてやる。
慎ましい彼等は、すぐには食卓につかない。私がテーブルを調えるのを、はるか向こうでじっと待ち、私が家の中に入ると遠慮がちにテーブルに近寄り、そして、誰か他のお客が同じご馳走を待っていないかどう探り、もしいるとしたら、まず彼等に先をゆずり、そうして初めて、おちょぼの口元にほんのわずかの食事を運ぶのである。
おなかが空くから食べる、からだを暖めるために食べる、子供のために食べる、と動物たちの食べ方はとても本能的だけれど、それだけに、目的が果たされればそれ以上の量は食べない。利己的でも飽食でもない。
「外に出てきてごらん、野兎が……!」
悲鳴にも似た夫の呼び声。駆け付けてみるとどうだろう、わが愛犬が、野兎を無我夢中で貪っているのである。ハンターが山に入って撃ち、猟犬が見つけ損ねた獲物を、放し飼いの犬がありついたのだ。
私は犬を叱る気にはなれなかった。それが動物たちの自給のあり方であり、自分の命を他のものに食物として与えるという、食物連鎖の宿命であるからだ。彼等は、分け合って食べるための丸いテーブルを持っている。
それにひきかえ、人間はどうだろう。世界各地で戦争や自然破壊をし、罪もない子供やお年寄りを飢えさせている。その引き金を引いた者が、食物や利益を貪っているのだ。そして今日、この雪の寒さに震え、食事もできず、温かな寝床もない若者を含む多数の人々が、コロナ禍のために苦しんでいるのだ。そんな報道を観ると、なんとかして上げたい、と思うのだが、それ以上に、そんな人々を助けない政治に怒りが爆発する。
ああ、真っ白な牡丹雪が吹雪く。雪よ、この真っ黑と化した世界を、真っ白な清潔さで、清浄にして欲しいのです。
静かなるエッセイ 「冬から春への花」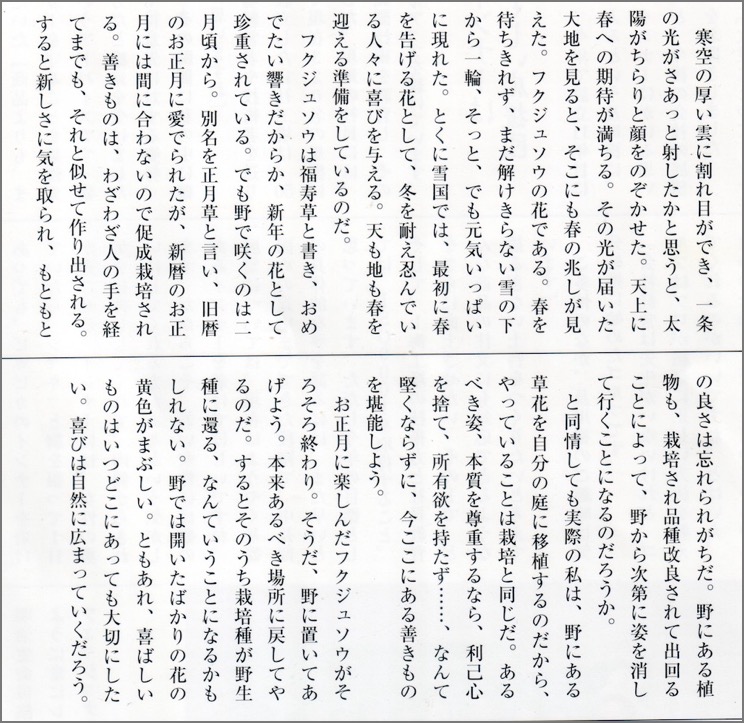
「福寿草」写真・エドワード・レビンソン
ブログのタップ



